 |
 |
誰ハロサブストーリー |

|
| |
| 「マリーの場合」 |
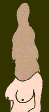 |
 |
|
| |
|
 |
20年以上前の本牧。「ホンモク」は不思議な街だった。
横浜でもないし米軍基地のある横須賀でもない。
米軍の家族が住む「ハウス」はあったけどとっくの昔にない。
とにかく昔の話。
「みなとみらい線」も携帯電話も「歩行禁煙ダメ法」もない時代。
その頃カオルはカネを持っていた。
少々キケンのある「非合法の商売」を手伝ってたから。
そんで「酒とロックの練習」のために悪友と本牧のバーにいった。
L字型のカウンターと4人掛けのボックス席がふたつ。
そしてジュークボックス。よく酔っぱらったネイビーにソウルをおごってもらったな。
店の名前はどうでもいいや。小学生でも読めるアルファベットが5つ並んでる店。
金曜日の夜なんとなく暗黙の了解で
カウンターのすみっこにあるその席は
マリーのために空けられていた。
そう。そのヒトはマリーと呼ばれていた。
彼女はいつもヒトリで店にやってくる。
バンドマンも元バンドマンもニセ芸術家も黒人の兵隊も
マリーが来ると彼女を意識してかあまりはしゃがなかった。
彼女は夏でも秋でも長いさらっとしたスカートをはいていた。
髪の毛は腰のあたりまである長くて少し茶色い髪。
ライムが飾られたジン・ロックを3杯くらい飲んでいた。
誰とも話さなかったし誰も話しかけなかった。
たまに「新参者」がマリーを口説こうとすると
黒人の海軍兵に外へ連れ出されることになる。
マリーは兵隊さんに「ありがとう」を言わないからオレ達がかわりに言った。
そしてその兵隊さんを「ポパイ」とあだ名した。黒いポパイ。
彼女はどんな曲でもよかったらしくソウルやロックに合わせて
カウンターをまっ赤な長い爪でコツコツとリズムをとっていた。
マリーはロングピースを吸っていた。
女の子でそれを吸っている人をカオルは今のところマリーしか知らない。
マリーの吸い殻はほぼ同じ長さで灰皿の中に「暖炉の薪」のように重ねられていた。
まっ赤な口紅つきで。
カオルがマリーと接触したのは1度。
何の特徴もない天気の夜だった。
その店にはトイレがなくいつだって廊下の蛍光灯は切れかかっていた
トイレはその廊下の突き当たりにある「雑居ビル共同トイレ」だった。
カオルがトイレに行き用を済ませて出ると廊下の壁にもたれてマリーがいた。
男女用もない1つしかないトイレだからマリーは「順番待ち」だと思った。
すれちがうちょっと前にオレは言った。「お先に」
そしてマリーの前を通り過ぎたときいきなりシャツの袖を引っ張られた。
「え?」
ハイヒールを履いているせいもあったのだろうけれど
カオルよりマリーはクビひとつぐらい背が高かった。
泣いていた。化粧が黒く流れるほど泣いていた。
オレの肩にアゴを乗せた。何も訊けなかったし何も言わなかった。
ただ泣いていた。ひたすら沢山泣いていた。
オレは迷ったけどチカラを入れずにそっと背中に手を回し少し撫でた。
思っていたよりマリーは華奢で「ガラス製の鳥カゴ」みたいに細かった。
とても素敵な「おしろい」みたいな匂いがした。
数分後(数十秒後?)彼女はオレのシャツで涙を拭きながら「ありがと」と言った。
思っていたよりマリーの声は低くて
「風邪をひいたジャニス・ジョップリン」みたいだった。
それっきりだ。
メールアドレスも携帯番号の交換もない。
用があったらマスターに伝書バトになってもらうしかないのだ。
そのあと2〜3回店に顔を出したらしいけれどその冬からもう彼女は来なくなった。
「長髪の坊や」にと新しい黄色いシャツをマスターに預けてくれた。
彼女の消息に関しては色々ウワサになったが
「千葉の方に郵便局員と結婚して暮らしている」というのが定説だ。
トイレのらくがき・金曜日の夜・コカコーラのベンチシート。
ジュークボックス・冗談のヘタクソなマスター・黒いポパイ。
そんなこんなをカオルは愛していた。もちろんマリーを特別に。
その一角はバブル崩壊ともに駐車場になり
現在は大量電化店になった。
「マリーがオレの肩で泣いた」ということはずっと誰にも話せなかった。
いや。話さなかった。なにかが致命的に壊れてしまうような気がして。
でもあれから20年以上たった。オレも予想をはるかに越えて40歳になった。
春には41歳になるからもう「時効」だろ。
この話を読むときにピッタリのBGMは
ギルバート・オサリバン「アローン・アゲイン」だ。
TSUTAYAにあるぞ。
便利な世の中になりました。ねえマリー姉さん。
おしまい。
|
| |
|
| |
topへ↑ |
| |
|
|